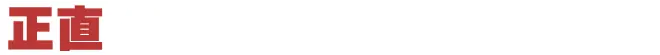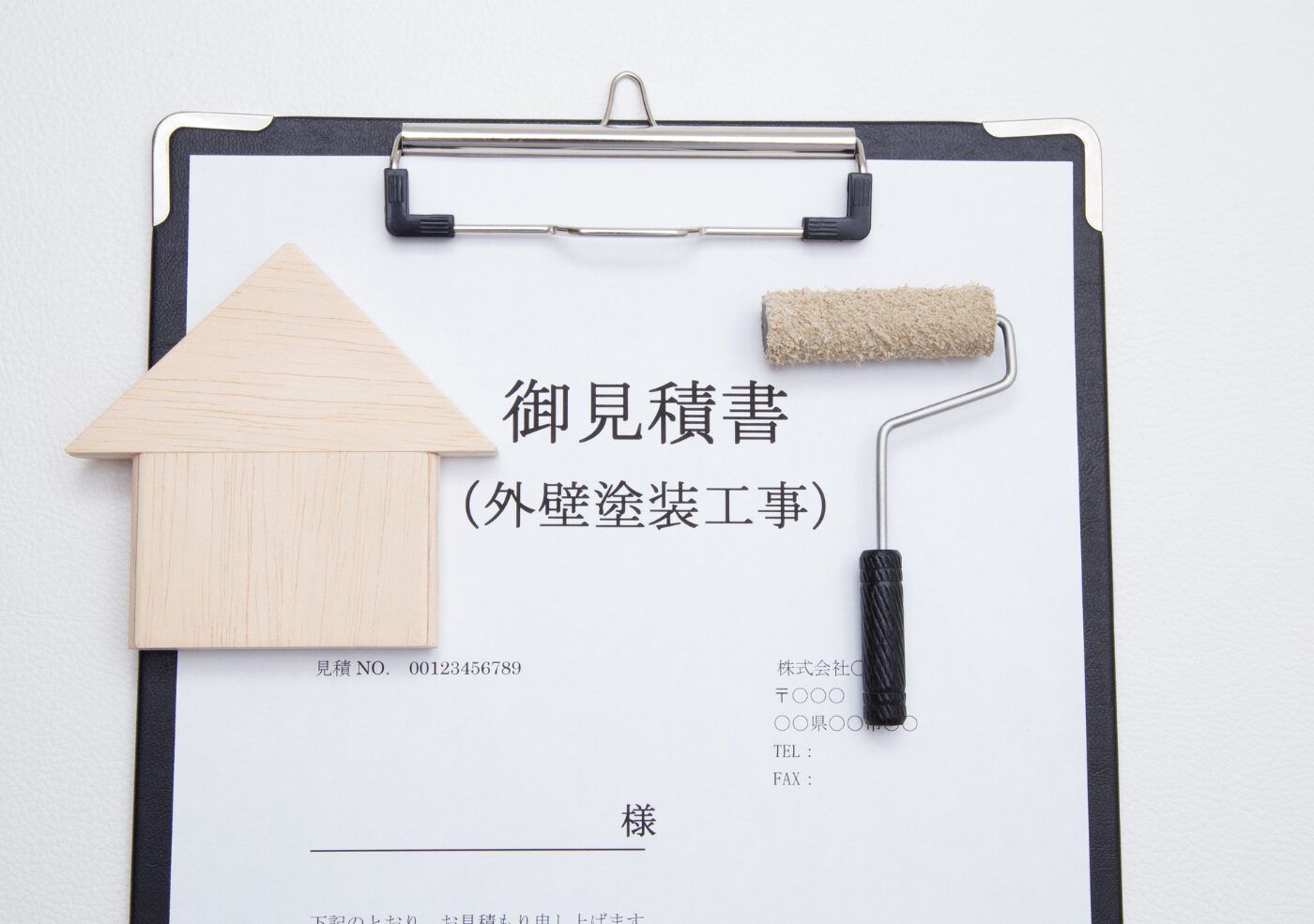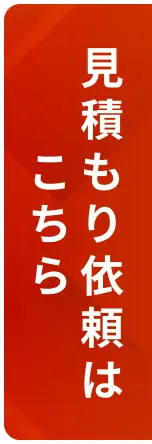住まいは時間の経過とともに外壁の汚れやビや藻、苔が目立っていきます。放置すると範囲が広がり、住宅全体が古ぼけた印象になってしまうことも。
そこで検討したいのが外壁の塗り直し。外壁塗装すると、汚れやカビの目立った壁が新築時のように生まれ変わり、住まいの傷みの進行を抑えることにもつながります。

失敗例も交えながら、外壁塗装の色選びを成功させるコツを紹介していきます。
押さえておくべきこと
- 施工不良なら再塗装できる
- 部分塗装で対応も可能
- 色選びは時間や天候による変化を想定する
- 実際の住宅をみてイメージする
外壁塗装の色がイメージと違ったらどうする?再塗装できる?
色選びの失敗なく外壁塗装を実現させることは、誰もが憧れる理想ですよね。しかし何事においても予期せぬトラブルはつきもの。外壁塗装でも色選びの失敗を絶対に防げるとは言い切れません。
施工不良なら業者に再塗装を依頼する
失敗の原因が明らかに業者の施工不良なら、保証期間内に業者に再塗装を依頼しましょう。施工不良の例としては、下記のようなケースが挙げられます。
施工不良の例
- 指定していた塗料と別の塗料が使われた
- 塗膜が均一になっていない(塗りムラ)
ただし、再塗装を依頼するには次のような条件が必要です。
再塗装できる条件
- 契約書に定めた保証期間内であること
- 保証内容に定められた範囲で再依頼であること
保証期間が過ぎているときや、「仕上がりが想像と違う」というような個人の主観に基づくときは、再塗装の対象外となるので注意が必要です。
気になる箇所だけ部分塗装でやり直す
仮に色選びやデザインに失敗したとしても、全面的なやり直しには多くの手間や経費がかかります。やり直すとしても、気になる箇所のみの「部分塗装」で負担を最小限に抑える方法もあるでしょう。
次の塗装時(約10年後)に備える
思い通りの色やデザインにならなかったといって手直しを繰り返せば、その都度多くの費用がかかってしまいます。失敗と感じるのは、以前の外壁色など「比較の対象」があるからで、見慣れてしまえば案外しっくりくるものかもしれません。
「失敗した」と我慢を感じながら毎日を過ごすのもストレスのもと。経験を糧に、次の外壁塗装(約10年後)がよりよいものになるよう気持ちを切り替えましょう。
外壁塗装については、規定の条件を満たす場合に公的な助成金制度を使えることもあります(条件は自治体などによって異なります)。次の外壁塗装時にこうした制度を利用するのもよいでしょう。
外壁塗装の色選び【失敗する4つの理由】
塗装作業では外壁の汚れやカビ、藻、苔などを除去し、施主が選んだ色をその上に重ねていきます。
住まいの条件と色選びがミスマッチを起こすと、外壁塗装が失敗につながることも。後悔しないよう、色選びで失敗を招く理由を4つ紹介します。
色選びで失敗を招く4つの理由
- 仕上がりが前もって確認できない
- 経年変化を予測しにくい
- カラーシミュレーションに頼りすぎる
- 色見本やサンプル板に頼りすぎる
仕上がりが前もって確認できない
外壁塗装に当たっては着工前に完成イメージを膨らませ、施主と施工業者の合意の下で作業を進めます。しかし、あくまでも双方の合意の手がかりは「完成イメージ」。施工が終わり、業者に「イメージと違う」という声が寄せられるケースも多く見受けられます。
外壁はフラットなものから凹凸のあるものまで様々です。塗料の塗り方や陰影によって見え方が違うので、これもイメージ通りの外壁にならない要因の1つです。
カタログを参考にして色を選ぶ時には、カタログ掲載の見本だけを参考にしても完成時のリアルな質感などは確認できません。実際の仕上がりを前もって確認できないのが色選びの失敗を招く理由の一つとされます。
経年変化を予測しにくい
外壁に使われる塗料の種類によるグレードがあり、カラーバリエーションや目安となる耐久年数などが異なっています。そのため、色の好みだけで塗料を選ぶと「思っていたより傷みが早く進んでいる…」という結果にも。

色の好みだけで塗料を決めるのでなく、メーカーが示している耐久年数の目安も含めて総合的に判断するようにしましょう。
カラーシミュレーションに頼りすぎる
カラーシミュレーションとは、パソコンに自宅の写真を取り込み、専用ソフトで屋根色や外壁色を模擬的に確かめる方法をいいます。この方法を使うと、自分の好きな色で外壁を塗装した時の仕上がりイメージを確認できます。
しかし、専用ソフトで確認できる仕上がりイメージもあくまで模擬的なもの。

カラーシミュレーションに頼りすぎることも、色選びやデザインで失敗する理由の一つです!
実際には、自宅周辺の景観や光の当たり具合など、目で感じる外壁の色はさまざまな要素で左右されます。シミュレーションで見た組み合わせが今の住まいにマッチするとは限りません。
色見本やサンプル板に頼りすぎる
外壁塗装の色選びをする時、小さな色見本(カラーチップ)やサンプル板などを使うことがあります。いずれも小さな面積の見本なので、外壁として塗装された時に思ったような雰囲気にならない場合もあります。

色見本やサンプル板を信用しすぎて失敗に至るケースも多く見受けられます。
外壁塗装の色選び【よくある失敗例】
ここまで見てきたように、外壁塗装の仕上がりがイメージ通りにならないことはしばしば起こります。よくある失敗例としてはどのようなものがあるのでしょうか。9つのケースをピックアップしました。
色選びでよくある失敗例【9選】
- 思っていたより色が薄くなった
- 汚れや色あせが目立ってしまった
- ドアや屋根と色の相性が合わなかった
- 思っていたより赤っぽく仕上がった
- 近くの家とそっくりの外観になった
- 周辺環境と合わない外観になった
- 配色のバランスが悪かった
- 業者任せにしたら思っていた色と違った
- 以前と同じ色で依頼したのに違う仕上がりになった
色が薄くなった
カラーシミュレーションに頼ってしまい、イメージした仕上がりと違ってしまったケースです。シミュレーションはあくまで擬似的に仕上がりを確かめる方法なので、自宅周辺の景観や光の当たり具合など、さまざまな要因で見え方が異なってしまうのです。
想定外の見え方となる理由の一つに、「面積効果」も挙げられます。「面積効果」とは、同じ色を塗った面を見た時に、小さい面積より大きい面積の方が色が薄く見えてしまう知覚効果のこと。「思っていたより色が薄くなってしまった」という失敗例では、面積効果が原因となっていることもあります。
汚れや色あせが目立つ
ブルーやグリーンなどの色は鮮やかさが特長である反面、酸性雨などの影響で色あせしやすいのが短所。これらの色を外壁に使い、2~3年程度で汚れや色あせが目立ってきてしまったというケースです。
だからといって鮮やかな色が外壁に適していないわけではありません。通常の塗料と原料がやや異なる「ラジカル塗料」を使うと、ブルーやグリーンなどの色でも汚れや色あせを長期的に防げる可能性があります。

ドアや屋根と色の相性が合わない
壁の色1のことばかり考えて、ドアや屋根との相性で失敗してしまったケースです。外壁に使いたい色があったとしても、玄関ドアや窓、サッシ、屋根などとの色の相性が悪ければ全体的にアンバランスな仕上がりになってしまいます。

住宅全体の配色を思い浮かべながら、慎重に色選びを進めていきましょう。
赤っぽく仕上がった
色選びをする際に、時間帯など環境による見え方の違いを考慮しなかったケースです。外壁色の見え方は、朝や夕暮れ時には赤みがかって見えたり、昼間は青っぽく見えたりと、時間帯や天候などの条件に左右されます。
色選びではカタログや色見本を使うことが一般的ですが、小さなサンプルで見た時の感じ方がすべてではないということを心に留めておく必要があります。
近くの家とそっくりの外観
住宅周辺の景観に合わせて色を選ぶのはとても重要です。しかし、そのことを意識しすぎて近くの家とそっくりの外観になってしまったというケースです。
景観を考慮した上で自分の好きな色を選ぶには、カラーシミュレーションを活用するのも一つの手。「シミュレーション頼み」は失敗を招く一つの原因となりますが、うまく活用すれば力強い味方になってくれます。
周辺環境と合わない外観
好きな色を使って外壁塗装をしたら、周辺環境になじまなかったというケースです。好きな色を使って外壁塗装をしても、近所の家や街並みなど周辺環境との調和が取れないと、俗に言う「浮いている」状態になります。
たしかに、自分好みの色を選ぶことは外壁塗装では重要なポイントです。しかし、周辺環境にも十分配慮しないと、変に目立つ上に近隣の人たちの反感を買う可能性もあります。地域協定などの分譲地では規定もあるので要注意です。
配色のバランスが悪い
2色の塗料を使ったツートンカラー(バイカラーとも)で外壁塗装したところ、配色を間違えてかえって見た目が悪くなってしまったというケースです。
典型的なものとして、「暖色系」であるオレンジと、「寒色系」であるブルーをツートンカラーとして使ってしまったケース。異なる色系統の組み合わせは、今ひとつのバランスを招く原因ともなります。ツートンカラーを取り入れたいときは、配色バランスに十分注意しましょう。

業者任せにしたら思っていた色と違う
例えば、あなたは「白」と聞いてどんな色を思い浮かべるでしょうか? スノーホワイトのような純白に近い色、やや黄色がかったアイボリーホワイトのような色…このように、同じ「白」といっても思い浮かべる色はまさに十人十色です。
業者に色選びを任せて失敗したというケースでは、このように言葉だけで色を決めたのが原因となることがしばしば。色選びでは、色見本やサンプル板など、目で見て共有できる材料を交えて業者とコミュニケーションを進めるようにしましょう。
以前と同じ色で違う仕上がりになる
外壁の経年変化による色あせを考慮せずに依頼したときの失敗例です。「同じ色で」といっても、色あせした外壁の色を基にするか、新築時の色を基にするかでは仕上がりに大きな違いが生まれるからです。
ここでもやはり、「同じ色で」と言葉のやりとりだけで工事に取りかからないのが失敗を未然に防ぐコツ。色見本などビジュアルで分かるツールを使い、施主と業者とのイメージを共有することが必要です。また、最後は申し合わせをして議事録にて確認することをお勧めします。

外壁塗装の色選び【成功させるコツ14選】
外壁塗装には作業足場なども必要で、塗装と足場設置の総費用が百万円を超えることもあります。お金をかけて施工するなら、色やデザインなど理想的な選択をして仕上げたいですよね。
色選びやデザインを成功に導くためにはどんなコツがあるのでしょう? 14のポイントをまとめました。
時間や天候による変化を想定する
外壁色の見え方は環境によって変化します。例えば、曇りや雨の日には暗めに見えたり、夕暮れ時には赤みがかって見えたりと、その見え方は時間や天候などの条件に左右されます。
したがって、そうした見え方の変化を想定して色を選ぶのも成功のコツの一つです。可能なら、時間帯を変えて色見本やカタログなどを屋外で見てみてもよいでしょう。
色を決めたら業者と書面を取り交わす
施工前のコミュニケーション不足で、業者が色を誤って塗装するケースもゼロではありません。間違いに気付いても、契約書に色に関する取り決めがなければ手直しなどの請求ができません。こうした事態を防ぐため、契約書には色に関する取り決めも記すのがおすすめです。

試し塗りしてからを塗装する
契約時に取り決めをしておくと、最初の工程である「下塗り塗装」の後に試し塗りに応じてもらえることもあります。試し塗りをすれば、色見本、カタログ、サンプル板などでは分かりづらい質感が分かり、塗装完了後の状態をより確実に把握することができます。
ただし、試し塗りは業者にとって手間のかかる作業となります。業者側から提案されなければ、応じてもらえるかを事前に確認してみましょう。
ツヤの有無で印象が異なる
ツヤの有無で外壁塗料を分けると、下記のように分類できます。
ツヤの分類
- 全艶(ツヤあり)
- 三分ツヤ
- 五分ツヤ
- 七分ツヤ
- ツヤなし
このように、塗料のツヤの度合いはさまざま。ツヤの有無は色と同時に決めることが大半ですが、ツヤの有無で見え方が大きく異なることも知っておきましょう。
ツヤと塗装色による見え方は一般的に次のような関係があります。
| ツヤあり+暗めの塗料 | シックな雰囲気 |
| ツヤなし+明るめの塗料 | 明るい雰囲気 |

塗料を選ぶ時は色だけにとらわれず、ツヤの有無もしっかり確認しましょう。
「面積効果」にも心くばり
「面積効果」とは、同じ色を塗った面を見た時に、小さい面積より大きい面積の方が色が薄く見えてしまう知覚効果のこと。前述の「色選びのよくある失敗例」でも紹介したように、面積効果にもしっかりと心くばりしましょう。面積効果を考慮せずに外壁色を選ぶと、予想していたのと異なる仕上がりになる可能性もあります。
ツートンカラーは配色に注意
外壁の個性を際立たせる、2色仕上げのツートンカラー(バイカラーとも)。効果的な色選びができれば外壁塗装は成功となりますが、そのぶん、慎重に配色を考える必要も出てきます。
例えば、「暖色系」の色と「寒色系」の色との組み合わせ。こうした組み合わせでのツートンカラーは見た目の悪さにつながってしまいます。
ツートンカラーの組み合わせに自信がなければ、配色の専門家であるカラーコーディネーターなどのアドバイスを受けるのも一つの手です。
カラーシミュレーションだけに頼らない
専用ソフトで屋根色や外壁色を模擬的に確かめる「カラーシミュレーション」を使うと、外壁の理想的なイメージが湧くかもしれません。
しかし、隣接する家の外壁色など周辺環境、面積効果などによる見え方の印象はカラーシミュレーションでは分からないもの。カラーシミュレーションはあくまでも参考資料の一つと留め、それだけに頼った色選びをしないように心がけましょう。
カラーコーディネーターなどの専門家に相談する
色選びやデザインに必要な情報を事前に調べたとしても、実際に活用できる情報はほんの一握り。他方で塗装業者の持つ情報もそれだけで十分とは言い切れません。なぜなら、塗装業者は「塗装技術のプロ」であり、色選びやデザインに関して深い知識を持っていないケースがあるからです。
塗装業者だけで十分カバーできない情報があれば、配色の専門家であるカラーコーディネーターにも相談するとよいでしょう。外壁塗装の色選びやデザインに関する情報を専門的な視点で助言してもらうことができます。
実際の家の外壁塗装を参考にする
自分のイメージに近い実在の建物を参考にすると、デザイン、色、外観などについてのリアルな質感を確認できることがあります。色見本やカラーシミュレーションなどを活用する一方で、理想的な配色をしている実在の建物を参考にするのも有効な手段と言えます。
近所の家と街並みの環境を確認する
前述の「色選びのよくある失敗例」でも紹介したように、近隣の景観を考慮した配色をしないと「浮いた」雰囲気で仕上がることもあります。周囲の景観や環境とのバランスが悪いと、住宅全体の雰囲気が崩れてしまうことにもなりかねません。
思い通りの色で外壁塗装に仕上げたいところではありますが、近隣の景観も考慮して色選びをすることも外壁塗装を成功に導くコツです。
できるだけ大きい色見本で確認する
色見本を併用するときは、できるだけ大きな面積の色見本を使うようにしましょう。小さな面積の見本だけで色選びすると、前に述べた「面積効果」で思いがけない仕上がりになる可能性があるからです。
色見本は日光の下で確認する
1日の約3分の2は屋外が明るい時間。つまり、外壁は1日の約3分の2を日光に照らされることになります。実情に沿った色の見え方を確かめたいなら、屋外が明るい時間帯に日光の下で色見本を見てみるのがおすすめです。
クリア塗装の導入も検討してみる
「クリア塗装」とは、無色透明な塗料で塗装をする工法のこと。色のない塗料で塗装を行うため、外壁本来のデザインを生かした工事が可能です。面積効果による影響も比較的少なく、外壁本来の色や柄が気に入っている方におすすめの工法です。
シンプルに単色塗装で仕上げる
前に述べたように、ツートンカラー(バイカラー)で塗装するときは、「暖色系」「寒色系」のような配色を十分に考慮する必要があります。一方、1色だけを使う「単色塗装」なら、面積効果や周辺環境とのバランスに注意することで大きな失敗を招く可能性が低くなります。
外壁塗装の色選び・イメージでよくある質問
-
色選びに失敗した場合、業者にクレームをつけることはできる?
-
施工不良であればクレームが可能ですが、好みの問題では難しい場合が多いです。
-
どのような塗料を選ぶと色の変化が最も少ない?
-
高品質な塗料や耐久性・耐候性が高い塗料を選ぶことで、色の変化が少なくなります。一般的にはフッ素塗料や無機塗料が高耐久の塗料です。
-
カラーシミュレーションのどのくらい信頼できますか?
-
シミュレーションは参考程度で、実際の仕上がりとは多少異なることがあります。大型の色見本も参考にするのもおすすめです。
外壁塗装における色選びのポイントまとめ
最後に改めて、外壁塗装の色を選ぶ時のポイントを3つ挙げます。
色を選ぶ時のポイント
- 色選びを失敗するケースの理由を知る
- より確実な色選びができるコツを実践する
- 仮に失敗した時の対処法を知っておく
これら3つのポイントを押さえた上で、以下のような失敗を招かないよう、入念に色選びをして理想的な外壁に仕上げてください。